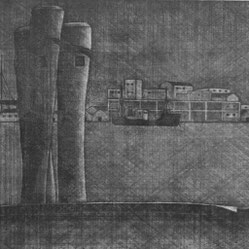
画廊通信 Vol.135 沈黙の宇宙で
浜口陽三と云う作家を知ったのは、この仕事に入って
間もない30代初めの頃、「版画芸術」という専門誌の
特集においてであった。恥ずかしながらどんな作家かも
皆目分らず、何とは無しにページを繰っていたのだが、
掲載されていた「黒いさくらんぼ」という作品を見た瞬
間、私は何故か目が離せなくなり、じっと見入っている
内にある不思議な感慨に襲われた。その時の事は、未だ
によく覚えている。何と言ったら良いのだろう、ふっと
心が浄化されて、深く穏やかに澄み渡り、そこに作品が
瞬時にして浸潤し、作品と自分とが「同化」したような
感覚──というような説明も、実は後で言葉にでっち上
げただけの話で、きっとそんなプロセスが有った訳では
なく、全ては同時に生起したのかも知れず、本当の所は
自分でもよく分らないのだけれど。いずれにしろ今にし
て思えば、それは私にとって初めての「本物」に触れ得
た体験であった。以降めったに無い事ではあれ、本物と
云える芸術に出会った時は、いつも決まって同じ感覚が
湧いて来て、いつしか私は逆にその感覚を基準に、作品
を判断するようになって行った。作家との出会いをよく
覚えていると云うのは、その謂である。こうして顧みれ
ば、その邂逅によって私は決定的な芸術観を刻印された
のであり、それほど浜口陽三という作家の生み出す宇宙
は、その極めて静謐な相貌の陰に、ある種深淵とも云え
る強靭な存在感を、限りなく豊かに孕むものであった。
浜口陽三、1909年和歌山県に生れる。生家は、銚
子市で江戸期より代々醤油製造業を営む名家ヤマサで、
父が10代目であったと言う。6歳の時に銚子に移住、
18歳で東京美術大学(現在の東京芸大)彫刻科に入学
するも3年後には中退、フランスに渡り独学で油彩の研
鑽に励み、サロン・ドートンヌ等の美術展に出品しなが
ら、30歳で大戦の勃発によって帰国を余儀なくされる
まで、パリを拠点に自由な活動を謳歌した。戦時中は、
通訳として旧仏領インドシナ(現在のヴェトナム)に滞
在したがマラリヤを発病して帰国、戦後しばらくは伊豆
で療養生活を送り、銅版画を本格的に始めたのは、よう
よう40歳を目前にした頃である。それより2~3年を
経た頃から、当時はまだ未知の技法であったメゾチント
に着手、40代半ばで再び渡仏してパリにアトリエを構
えて後、前代未聞とも言える「カラー・メゾチント」技
法を開拓して、今に残る独自の世界観を湛えた名作を、
地道な制作の中から次々と生み出す。1957年(48
歳)、サンパウロ・ビエンナーレにおいて版画大賞を受
賞、1960年にはヴェネチア・ビエンナーレに出品、
翌61年にはリュブリアナ国際版画ビエンナーレにおい
てグランプリを受賞、5年後のクラコウ国際版画ビエン
ナーレにおいても特別賞を受賞する等、国際美術展を舞
台に立て続けの受賞履歴を重ねながら、新たな銅版表現
を拓く類例なき芸術家として、その名を不動のものとし
て往く。70歳を過ぎた頃、30年近く住み慣れたパリ
を離れてサンフランシスコに移住、以降はその地を拠点
に意欲的な活動を続け、1986年にはここ千葉の地で
も「浜口陽三展<静寂の詩メゾチントの巨匠>」と銘打
たれた巡回展が、県立美術館を舞台に開催された。それ
から10年後、87歳の時に故郷の日本へ帰国、ほどな
く作品を常設展示する専門美術館が立案となり、現在も
活動を続ける「ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション」
が日本橋蛎殻町に開設されるを見て、2000年と云う
世紀の変り目に没している。享年91歳であった。
以上、その生涯を駆け足で記してみたが、年譜を追っ
てすぐにも感じる事は、その悠揚とした遅咲きの歩みで
ある。むろん如何に裕福な名家の息子とは言え、加えて
三男であったそうだから、たぶん家業の継承は免除され
ていたにせよ、それにしても傍からは、青春から壮齢に
まで到る長い雌伏の時代を生きるその姿は、気ままに贅
沢に遊び暮らす、道楽息子にしか見えなかったのではな
いか。その間、いわゆるシュトルム・ウント・ドラング
(疾風怒濤)と言われる時期は、浜口にもきっと有った
に違いない。どうにもやり切れない青春の懊悩を、荒ぶ
る精神の抑え難き衝動を、カンヴァスにこれでもかと叩
き付けた時代は、確かに有ったのだろうけれど、その頃
の作品も残っていなければ、その頃を語る当人も既に亡
く、たとえ存命であったとしても、当人からそんな話の
聞ける機会は、たぶん無かっただろうと思う。何しろ、
浜口陽三ほど自らを語らない作家は居ないのだ。文献を
探したところで、僅かなインタビューの記事を見つける
ぐらいが関の山、たとえ見つけたにしても、創作の核心
に触れるような発言はほとんど無い。よって後世に残さ
れた者は、数多い評論等の資料を参考にする事はあった
にせよ、後は作品そのものを手掛かりとする他ない。そ
んな訳で、以降作品と資料だけから判断させて頂くが、
今回の出品作品中、最も古い作品は1951年の「月島
(杭)」で、作品の制作当時は42歳頃、つまりはメゾ
チントに着手した最初期の作品と云う事になるが、この
時点で既に、作品は浜口特有の静謐な情緒を湛え、更に
資料を垣間見れば、後年の主要なモチーフである果実を
描いた静物画も同年に登場しており、早くもそのオリジ
ナリティーが色濃く現れているのである。つまり、浜口
は最初から浜口であった。そこに、いわゆる「若描き」
と呼ばれるような未熟の痕跡は無い。と言うよりは、厳
しい完成度しか許さなかった作家自身が、自らの未完で
あったろう時期を、奇麗に消し去ってしまったと言うべ
きか。従って、初期からほとんど完成の域にあった浜口
の世界は、以降あたかもウィスキーが10年・20年・
30年と熟成を重ねるが如く、いよいよその深度と豊潤
の度合いを増して往く。そして、あくまでもゆったりと
した歩みの、孤独にして地道な道程の途上で、いつしか
その画面は「静物画」と云う範疇を遥かに超えて、かつ
て誰も表し得なかった「宇宙」へと到るのである。
今こうして顧みれば、浜口陽三を始めとした日本人作
家の活躍によって、メゾチントと云う技法は広く知られ
る事になった訳だが、ご存じのようにこの技術は、数あ
る銅版技法の中で最も手間のかかる工程を持つため、極
めて職人的な技巧を必要とするものである。それもその
はず、ヨーロッパにおけるその歴史を紐解いてみると、
17世紀に発明されたこの技法は、元々油彩画を精巧に
複製するための手段として、当時の版画職人が競って用
いたものであった。「メゾ=中間の」と云う言葉が示す
通り、数多い銅版技法の中で唯一、明から暗へと到る中
間の階調を表現する事が可能なため、絵画の微妙な明暗
の再現には、正に打って付けだった故と思われる。とこ
ろがその隆盛は長くは続かなかったようで、19世紀に
華々しく登場した写真技法によってその座は忽ちの内に
奪われ、余儀無くされた急速な衰退の果てに、技法自体
が遂には消滅してしまう。正に、絵に描いたような悲運
である。それからほぼ100年後、この世から全く忘れ
去られ、ヨーロッパ人の誰もが顧みる事の無くなってし
まった技法を、再びこの世に瑞々しく甦らせたのが、奇
しくも浜口陽三・長谷川潔といった邦人作家であった。
しかも彼等は、メゾチントを古い複製技法としてではな
く、新しい版画技法として用いたのである。よってそこ
から生み出された作品は、かつての油彩画を複製化した
表現とは、全く趣を異にする斬新なものであった。それ
だけでも美術史に画期的な足跡を残す偉業と言えたが、
浜口の成した更なる業績は、その技法を次には「カラー
化」すると云う前代未聞の挑戦である。言うまでもない
事だが、それまで銅版画というものは白黒だったのであ
り、色が欲しい時は上から塗るしか無かったのである。
それが証拠にもう一人の雄・長谷川潔だって、作品に色
彩を施すに当っては、版画の上に筆で彩色すると云う手
段を取っている。おそらく浜口の場合、世界最高の色彩
版画として名高い「浮世絵」を生んだ国の芸術家として
は、塗ってお茶を濁す事に甘んじては居られなかったの
だ。さりながら、モノクロ表現にも限りない可能性を読
んでいた浜口は、以降モノクロ作品と多色刷りによるカ
ラー作品を併行して発表すると云う姿勢を、生涯に亘っ
て崩さずに貫き通す。そして時には同じ作品を、モノク
ロ・バージョンとカラー・バージョンの二種で表現した
り、あるいは複数の異なるカラー・バージョンを発表し
たりと、その世界は万華鏡の如く千変万化を呈し、いよ
いよ多様なヴァリエーションを派生して往くのである。
浜口陽三のモチーフは、常にごく身近な物に限られて
いる。さくらんぼや葡萄、蝶やてんとう虫と云った、誰
もが見慣れたさりげない果実や小動物で、その世界はシ
ンプルに構成されるのだが、作家のフィルターを通して
それらが画面上に再現された時、元のイメージとは似て
も似つかぬ姿に変貌する。どこまでも深く沈み込んだ、
時には目を凝らさなければ見えない程にも暗い背景の中
から、それらは尊厳に満ちた命の如くに浮び上がる。そ
こには幽玄の趣を湛えた時空が生起し、その奥深い圧倒
的とも言える静謐の中より、しんしんと放射される強靭
な磁力が、見る者を内奥の限りない宇宙へといざなう。
浜口以降、日本人の特質に合っている故か、メゾチン
トと云う難儀な技法を巧みにこなす版画家が多い。彼等
は確かに器用ではある、しかし、器用を超えた何かを持
ち合せる作家は極めて少ない。例えば定番となった「さ
くらんぼ」を浜口のそれと較べてみると、その差異は歴
然とするだろう。他作家がただ「さくらんぼ」を描いて
いるのに対し、浜口は「さくらんぼ」を材料として用い
ながら、その奥に深い抽象の世界を宿す。そのため浜口
と並べてしまうと、悲しいかな他作家のメゾチント作品
が、巧みなだけの工芸品に見えてしまう経験を私は何度
もした。斯様に多くの作家が、単に精巧な具象版画を目
指すのに対し、浜口は具象をモチーフとはしながらも、
その世界は本質的に「抽象」を指向するのである。
60歳を過ぎた頃、浜口は長年に亘る眼の酷使で眼疾
を患い、メゾチントの制作が出来なくなった。幸い2~
3年で病気は快癒し、再び銅版の制作に復帰し得たが、
その間浜口は代替技法として、リトグラフの制作に集中
している。それはそれで軽妙洒脱、モダンな世界を創り
出しているが、その頃の浜口の心境は如何ばかりのもの
であったか。例によって当人は何も語ってないけれど、
おそらくは深い絶望と無縁では居られなかっただろう。
この時期の作品に「26のさくらんぼ」と云うリトグラ
フが有って、画集でしか見た事はないにせよ、それはま
るで灯の消えた電球が縦列を成して、深閑とした虚無に
沈むような作品だった。それから十数年を経て、浜口は
ほぼ同じ構図のまま、再び縦列のさくらんぼを銅版化し
ている。今回の案内状に掲載した「22のさくらんぼ」
である。この静かに発光するような輝きはどうだろう。
あたかも銅版に向き合える歓びを、そのまま熱く灯した
かのような作品である。浜口陽三と云う版画家は、徹頭
徹尾「銅版」の申し子なのだと思う。ここにはあの絶望
の時期を超えた作家の、甦った命を謳歌するかのような
凱歌が、深く温かく刻まれたメゾチントの宇宙の中で、
尽きる事のない灯火となって燃え続けている。
(14.12.29)
 山口画廊
山口画廊